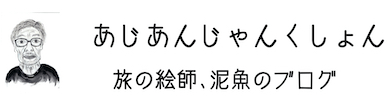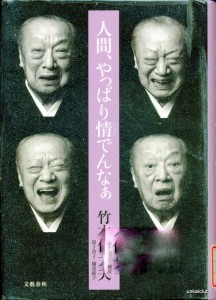竹本住大夫、「人間やっぱり情でんなあ」
わしがまだ受験生だった、遙か昔の頃、和歌山の田舎から大都会の大阪に出て
来て、純情な青年は、その賑やかさと喧しさと忙しなさにえらい驚いたもんや
った。今の丸ビルあたりやったかなあ、旭屋書店にはよく行った。裏口を出た
ら別館があって、確かその向かいに中華料理屋があってジンギスカンやら餃子
やらを食ってその美味しさにたまげたものだった。帰りがけにはまだ闇市跡の
ような妖しい店がならぶ一角があって怖い物みたさでドキドキしながら通った
ものだった。そういうあたりかどうか、戦後のどさくさでむりやりできた街で
はなくてもっと昔からの生活が色濃くあったころの大阪の街がこの人の話の中
から、まるで今でも行ったら出会えるかのような気分で立ち上がってくるのが
この人の話芸なんやろと感心する。
わしが子どもの頃に出会ったもの、竿竹売りや鋳掛けやさん、ポン菓子のおっ
ちゃん、街角のせんべい屋でくずのせんべいをもらったこと、チンチン電車に
ただ乗りして冒険旅行に、いろんなことはなんの脈絡もなくとりとめもないけ
ど、この人のように芸の道一筋の暮らしとからまって話が進むと自ずから舞台
の上を見ているような気分にもさせてくれる。
脳梗塞で倒れはってからの闘病生活はテレビのドキュメンタリーで見たことが
ある。最後の公演も聞きに行った。あれほどの凄まじい執念でリハビリを続け
ることができるのか、ここまで出来るように復帰したのに芸としては納得でき
へんのかとただ感動するだけであった。
世の中ではえてして、芸の技量の素晴らしさと人格、品位の高さとは一致しな
い人を見てがっかりする事がありがちなんやけど、この本で、この人の語りで
自分の人生を坦々と綴っていくなかから、ストイックなまでの厳しい精進の暮
らしと芸に対する愛情が育てた品格を十分感じることができてとても嬉しい気
持ちにさせてくれる。
そんな本であった。
山口恵以子、「食堂のおばちゃん」
東京の裏町に「はじめ食堂」という定食屋さんがある。日が暮れたら居酒屋さ
んになるというよくある下町食堂だ。一(にのまえ)二三子と言うふざけたよ
うな名前のおばちゃんと一子という語呂合わせのような名前の姑と2人で切り
盛りしている。元々、腕のある洋食店主だった一子の旦那が突然亡くなり、息
子が家庭料理の店として後を継いだものの又亡くなって、結局残された2人が
店を続けることになったのだ。この作家、食堂のおばちゃんをしながら松本清張
賞をとったというだけあって、食べ物の話、食堂の話はすばらしく現実感がある。
ここに出て来る料理のレシピが総て巻末に出ているから総ては作者の手の内に
あるということなのだ。
「月下上海」とはひと味違った展開だ。
何かを食べたら何かが起こる。
何かが起きたら何かを食う。
おいしいもんを食って、うまく世の中が治まってしまえばそれに越した事は無い。
そう言えば、昔々、若い夫婦が学生相手の洋風食堂をとてもリーズナブルな値段
でやっていて、日替わり定食を食べに毎日のように入り浸っていた頃もあった。
そう言えば、料理はからきし駄目なのに、そこに集まるお客さんたちの雰囲気が
面白くて通っていたような店もあった。
そう言えば、飲みながら議論ばっかり盛り上がって、折角の美味い酒や料理に
気がつかないで後で悔やんだような店もあった。
誰しも心の中に懐かしい食堂のおばちゃんがいてるようだと思う。
そして又新しい出会いがあったらいいなと思う。
そんな事を思わせるような本だった。
ブログランキングに参加しています。もしよかったらポチンとお願い致します。
![]()
にほんブログ村
ありがとうございました。